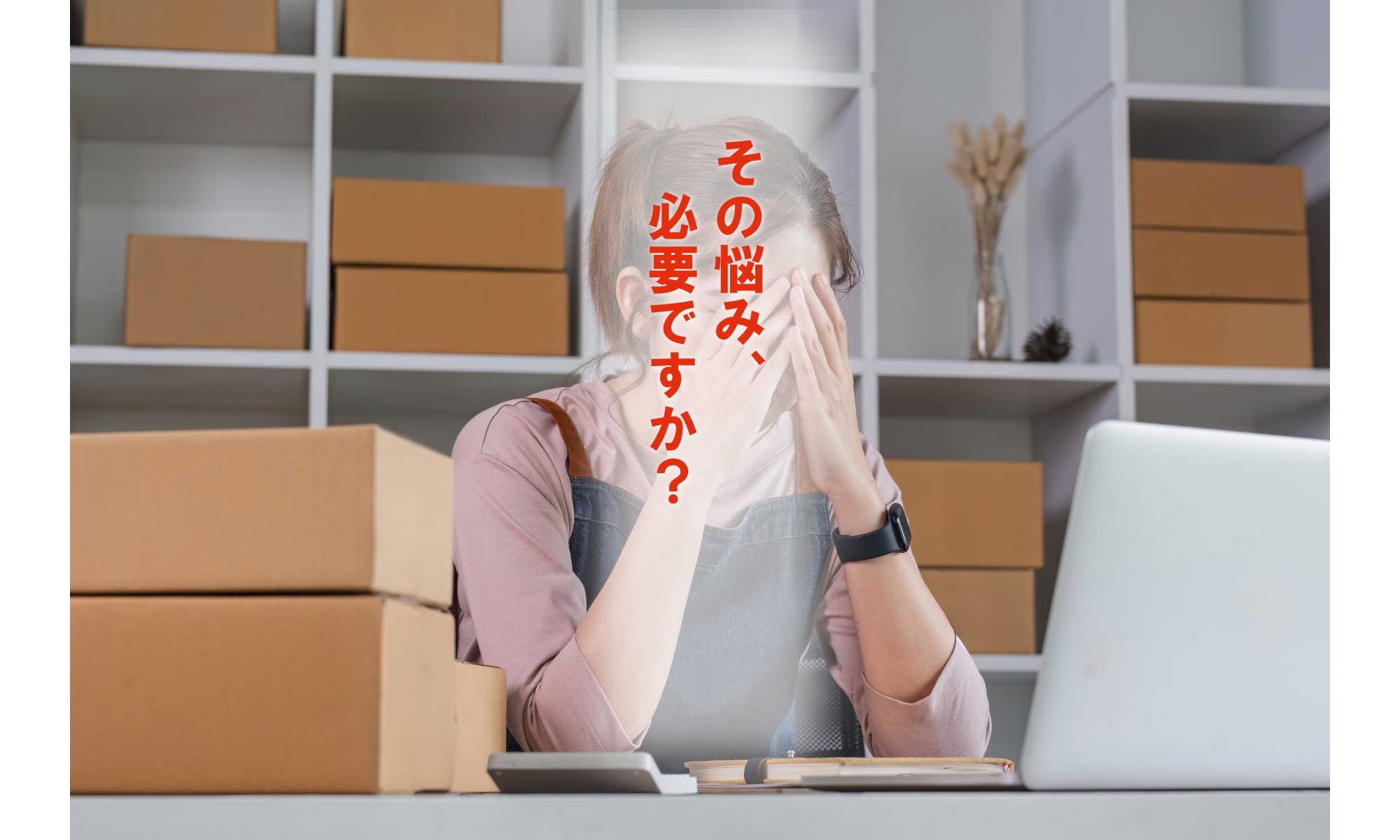クマ被害が過去最高ペースだ。
クマはただ生きているだけで、世界征服をもくろんでいるわけではない。
人のいる地域に来てしまい、動くやつがいるから敵かと思い攻撃しただけのこと。ヒグマの場合は食うつもりだったかもしれないが、それは自然の摂理だ。
野生の動物は生きていくために必死だ。
人間の作物を食い荒らすとか、人間に襲いかかるとか、それ自体は自然のことだから防御するしかない。
さて、どう防御するのか?
一旦視点を変えてみる。
最近、山間の農村に行くと、田や畑に電線が張ってある。イノシシ除けだ。
イノシシは昔から住んでいる野生動物だが、なぜ近年、人里に来るようになったのか?
理由はいくつもあるが、どれも納得できる。
1. 耕作放棄地の増加と人間活動の衰退
- 高齢化や過疎化により、農地が放棄され、藪や竹林が増加。
- これらの場所はイノシシにとって隠れやすく、餌も豊富なため、人里との境界が曖昧になっている。
2. 森林環境の変化
- 昔は焼き畑農業などで山が定期的に手入れされていたが、現在は放置されがち。
- その結果、竹や雑草が繁茂し、イノシシの餌場として適した環境が山から人里近くまで広がっている。
3. 温暖化による活動期間の延長
- 冬でも活動する個体が増え、繁殖力も高いため、個体数が増加傾向にある。
- 気候変動により生息域が拡大し、都市部にも出没するようになった。
4. 人間による餌付けやゴミ管理の不備
- 生ゴミや農作物の残りなどがイノシシを引き寄せる。
- 一部地域では餌付けが習慣化し、イノシシが「人里=餌場」と学習してしまう。
5. 狩猟者の減少と保護政策の影響
- 狩猟人口の減少により、イノシシの個体数管理が難しくなっている。
- 一時期の保護政策により、絶滅寸前だったイノシシが増加に転じた。
また、昔は山と人里との間に緩衝地帯があり、野生動物は人里に近づきにくい環境があった。この緩衝地帯とは、次のようなものである。
1. 里山(さとやま)
- 人が管理する雑木林や竹林、薪や炭を取るための森林。
- 定期的に手入れされていたため、藪が少なく、イノシシが隠れにくい。
- 人の気配があるため、野生動物が近づきにくい。
2. 畑や果樹園
- 山と住宅地の間に位置し、農作業が行われていた。
- 人の活動が多く、イノシシにとってはリスクが高い場所。
3. 水路・用水路・堤防
- 地形的な障壁となり、イノシシの移動を制限。
- 人工的な構造物が野生動物の侵入を防ぐ役割を果たす。
4. 集落周辺の空き地や草地
- 定期的に草刈りされていたため、視界が開けていてイノシシが警戒する。
- 人の生活圏との境界を明確にしていた。
これらのことを考えると、人の生活圏や生活習慣の変化によって、山と人の生活圏の境界が曖昧になってきたことは十分納得いく話だ。
クマを含め、野生動物が人の生活圏内に近づかないようにするためには、昔の生活環境を取り戻すことが良いかもしれないが、そんなことはかなり難しい。
田舎暮らしをしたい人が増えていると言っても、所詮は雀の涙。この広い日本中を変えてしまうほどには手が届かない。
公的な機関が議論してないのか?
調べてみたら、こんなのがあった。
日本学術会議という組織が行った公開シンポジウム
「増大する野生動物と人間の軋轢:これからの鳥獣管理と人間社会を考える」
残念なことに、会議の報告については出てないようだ。
日本の暮らしの中で、何か問題があれば解決に向けて話し合う人たちが出てくる。
素晴らしいことだ。
本来は、政治家がこうあってほしい。
身近なところで考えると、住んでいる地域や学校や会社、問題だらけだ。
この問題に対し、不満を抱えているだけで良いのだろうか?
何かできることはないか?
小さくとも集まれば大きな力になる。
そこを良くするのは、あなた自身だ。
もちろん私自身でもある(泣